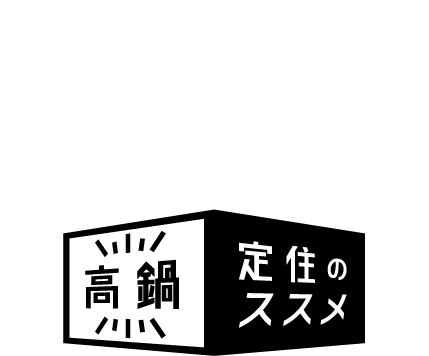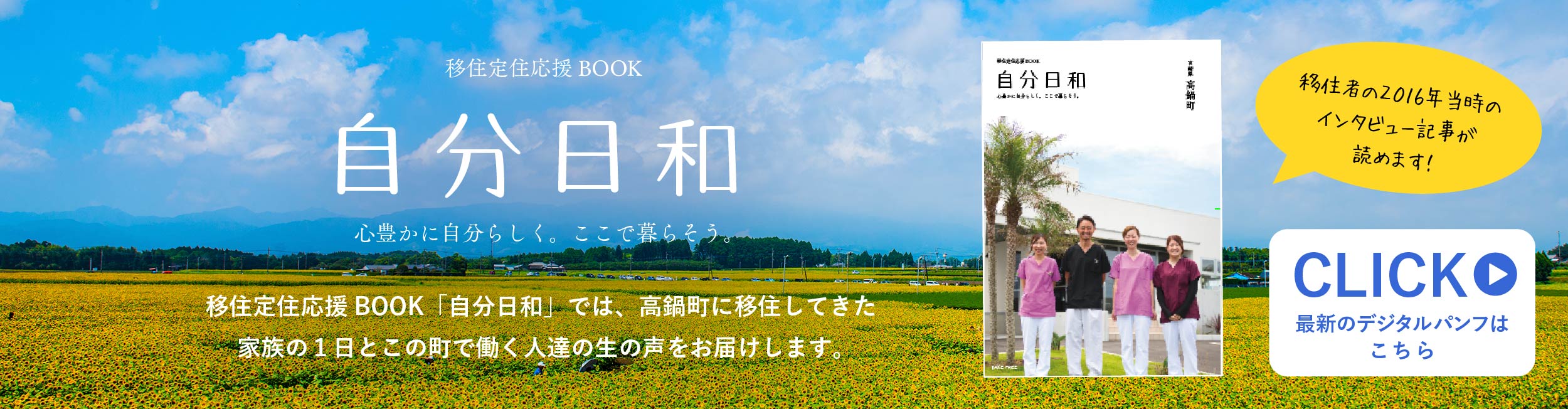移住者紹介
IMMIGRANT
移住7年目、「子ども食堂」に想いを込めて。
子ども食堂『にこっとごはん』
竹中 稔代さん

カメラに向かって笑いかけるピンクエプロンの女性と、恐竜の遊具。
温かな佇まいがどこか似た“ふたり”の笑顔は、子ども食堂『にこっとごはん』のシンボルです。
7年前、生まれ育った奈良県天理市を離れ、天理教高鍋分教会に嫁いだ竹中さん。それから1児の母となり、高鍋町民としてすっかり腰を落ち着けた2024年12月。満を持して、子ども食堂をオープンしました。
どのような想いで、この挑戦に踏み切ったのでしょうか。
きっかけは“友だちづくり”。

― 移住から時間が経ちましたが、当時の心境を覚えていらっしゃいますか?
結婚後数日でお引越しと、慌ただしいスタートだったのですが、はじめから高鍋の空気は私にしっくり馴染んでいたように思います。地元・天理市も自然と街が共存している環境で、このまちと雰囲気が似ているからかも知れません。夫の親族が温かく迎えてくれたこともあり、特に困るようなこともありませんでした。
ただ一つ挙げるとすれば、純粋に”友だち”と呼べる人がいなかったことは少し寂しかったですね。
子どもが産まれてからはママ友ができたりしてそれなりに充実していたのですが、もともと人と関わることが好きだったので、もっと友だちが欲しいなと思って。それが『にこっとごはん』をはじめた理由の一つでもあります。

〔食堂には、町内外から家族連れをはじめ老若男女が次々に訪れる。〕
― しかしどうして、「子ども食堂」なのでしょう?
子ども食堂を定期的に開いている教会は多く、天理教会のつながりで、活動自体はこれまでたくさん目にしてきました。その度に「楽しそうだな」とうらやましく眺めていたのですが、ある日、高鍋町社会福祉協議会から現物の支給(食材や箸・紙コップ、消毒液などの消耗品)などでバックアップいただけると知り、じゃあ私も始めてみようと思ったんです。
子ども食堂とは、無料または低額で利用できる地域の食堂のこと。「地域食堂」や「みんなの食堂」とも呼ばれていて、老若男女どなたでも利用できるものらしいんです。一人で食事をするのが日常になっている方が誰かに会いに来るのもいいし、家族みんなで来てもいい。つまり、「地域の交流の場」。活動を通して、誰かの、私自身の新しい居場所がこの高鍋町にできるかもしれないと思いました。
移住仲間の行動力に背中を押されて。
― 昨年(2024年)12月に第一回を開催したと伺いましたが、10月に一度プレオープンされていますよね?
はい。同じ移住者の藤居 優さんと合同で親子向けのイベントを主催し、そこでプレオープンを行いました。
藤居さんの娘さんとわたしの息子が同級生だったことから生まれた縁で、藤居さんも私も関西出身ということで意気投合。彼女がヨガインストラクターをしていて「10月にヨガのイベントをしたいけれど場所が見つからない」と言っていたので、「じゃあ教会を会場にして一緒にやりましょう!」と提案。8月からバタバタと準備を進めたのですが、彼女の行動力の素晴らしさといったら! 知り合いのネイリストやキャンドルアーティストなどの方々を招いて、さまざまなプログラムを親子で楽しめるイベントに発展していきました。
子ども食堂では焼きそば弁当を70食分も準備したのですが、開始30分ではけてしまう盛況ぶり! これにはとても驚きました。

〔親族の協力を得て大量の食事を準備。想定を超える来場者に、嬉しい悲鳴!〕
嬉しかったのは、これまでつながりが希薄だったご近所さんも足を運んでくれて、「また来るね」と声をかけてくださったこと。プレオープンはまさにてんやわんやの忙しさでしたが、期待していた以上の結果になり、ますますやる気に火がつきました。そして何よりも藤居さんの実行力にはたくさんの刺激を受けましたね。
子どもたちの成長への願い。
― 竹中さんの子ども食堂では、特徴的な取り組みをされていますよね?
はい、子どもたちが楽しめる手作りデザート体験なども取り入れています。第一回は「手作りパフェ」を、第二回は「手作りクレープ」を企画し、とても喜んでいただけました。

〔生クリームにアイス、さまざまなトッピングが準備してあり、参加者は自分の手で「オリジナルパフェ」を完成させる。〕

〔自分でつくったクレープに、思わず笑顔がこぼれる。〕
― どうしてそのような体験型プログラムを取り入れようと思ったのですか?
それは、料理にまつわる息子と私のとある経験が関係しています。
息子は自閉スペクトラム症で、料理動画が大好き。時折真似をしようとして台所を散らかしてしまうこともあり、私はそれを一生懸命止めていたのですが、ある時息子が割ってしまった卵を見てふと「一緒に(この卵を)ホットケーキにしよっか」と提案してみたんです。すると息子もホットケーキづくりに夢中になり、そこから数ヶ月はよく一緒にキッチンに立ちました。フライパンに顔を近づけすぎて火傷したりと、痛々しい失敗もありますが、それ以降は自分で気をつけるようになったりと学びもあり、「思いがけず踏み出した一歩が、子どもの成長につながることもある」という私自身の気づきにもなりました。この経験を皆さんにも味わってほしい、少なくともその“きっかけ”になればと、思いついた取り組みなんです。準備や後片付けの煩わしさがないぶん、親御さんも気軽に挑戦させられますしね。
それにもちろん、子どもたちが料理に関心をもってくれたらなという期待も込もっています。将来自立した大人になるために、料理はできたほうがいいですから。これは、私が息子に願うことでもあります。

〔息子の栞一(かんいち)くんと。〕
加えて私自身、学生の時は栄養士課程で学びながら教室に通うほどの料理好きで、中でも料理教室で過ごした時間は特別幸せでした。結局それを仕事にすることはなく20〜30代を過ごしてきたのですが、最近ふと当時の気持ちを思い出して、「料理教室を開きたい」という夢が蘇ってきたんです。ですからゆくゆくは、「親子クッキング教室」のような催しにも発展させていけたらなと考えています。
垣根を超えて、人と人がつながる場所。

藤居さんと「宮崎の人って親切で温かい。だけど少しシャイなところがあるから、初めが難しいんだよね」と話したことがあります。定住者でもその壁が超えられず、ご近所さんと疎遠なままってことも多いと思うんですよ。私自身もそうです。ですが、子ども食堂でぐっと距離が縮まった実感があるので、それを皆さんにも感じていただけたらいいなあと思います。
今後はボランティアを受け入れたりして人員を補充し、よりスムーズな運営と、楽しい時間を過ごせる工夫をプラスしていきたいなあと思います。
これからも2ヶ月に1度の開催を目標に継続していきますので、ぜひ気軽にお越しいただきたいです。